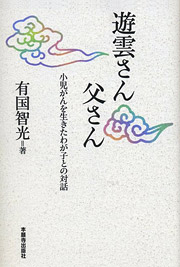
| 目 次 |
まえがき 第1章 まさか 第2章 日常 第3章 がん 第4章 死 第5章 生 第6章 そして あとがき 遊雲と小児がんとの三年 |
|---|
この世の中で何が悲しいといっても、わが子に先立たれるほどの悲しみはない。病気であれ、事故であれ、誰もがそういうことに見舞われないという保証はないのがこの世の生である。
だが、この本がすばらしいのは、まえがきにもあるとおり、「私たちはふつうならば嘆き悲しむしかない出来事を『楽しんで』いられる」とおっしゃっているところである。そして、「死はすばらしいご縁ですよ、ごまかして内に抱え込んでしまうのではなく、かけがえのない『今』を照らし出してくれる外として、顔を上げて出会っていきましょう」と結論づけていることである。
死を私と縁のないもの、とか、生の陰部として語るのでなく、生の「外」、生を輪郭づけてくれる外としてとらえることを教えてくれている。
著者の有国智光さんは私が学生時代に知己を得ていたのだが、それ以来、ご無沙汰のまま三十有余年がすぎ、今、この本に出会うというかたちで再会した。不思議なご縁としかいいようがない。人生には、不思議がある。それが人生に深い意味を与える。
まったく知らない人でないことからくる近しさから、この本を読みながら、自分を重ね合わせていたが、とても自分にはできない一心さで我が子の重い問題に取り組んでいかれた有国さんの真摯な姿と気迫がありありと伝わってくる本であった。
この本は、12歳(小学6年生)のご長男が小児がんを発病され、それから3年余りを父親としてお子さんと共にがんと向き合って歩まれ、さらに、浄土真宗、親鸞聖人の教えをいただく僧侶という立場から子どもの死というものをどう受け止めていくかを苦悩しつつ問いつづけられた赤裸々な回想の書である。
著者は「がんのほんとうの怖さは、現実の痛みにではなくて、『死ぬかもしれない』という宙ぶらりんさにある」と述べ、死を突きつけられることで、実は、はかなく脆いものだった生の本性があばかれたあやうい生に対するおびえである、ともいっている。
でも、彼は、切羽詰ったなかで、「でも、何があっても、大丈夫だからね」と口に出たという。「大丈夫だと言ってくださるのは阿弥陀如来です。何があっても、大丈夫。そう口にできる環境――ご縁――を恵まれていたことに、ただ、感謝しました」とも述べている。
死は、人によって3通りの現われ方をするそうだ。死を通じて虚無に出会う人、自己に出会う人、そして、仏と出会う人。そして、仏と出会うとは、「いのち」としての仏に会うことで、「死にたくない」というのは「永遠のいのちと出会いたい」という意味の叫びだ、という。
ご長男、遊雲さんの言葉として「死ぬことをきちんと考えるって、ほんとうはそんなに大変なことじゃなくて、今を精一杯楽しむってこと」という言葉をあげ、遊雲さんを「かわいそう」がる必要などなかった、遊雲さんは「死にかけて」いるのではない、いつもその時そのときにいのちを輝かせているだけなのだ、遊雲さんが今、ただ生きて静かに確かにいのちを輝かせていることは、そのまま父さんのおびえでありおののきであり、そしてそのまま父さんのいのちの輝きだった、という境地にたどり着いている。そして、親鸞聖人の慚愧は、「わが生のただ中に、生きて生かされたおののきであり、喜びであったに違いない」、といい、浄土真宗は、死後を問題にしているのではなくて、生者のための教えだ、ともいっている。著者は、この出来事を通して、浄土真宗の教えの深さをも極めている点でも、是非ご一読をお薦めする本である。







